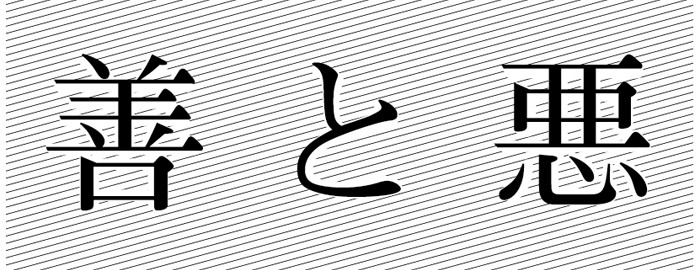
序
二〇一三年、初めて雪の降った夜のことだった。僕は東京の西の外れにある自宅近くの大衆居酒屋に腰を据えて、一つの企画について考えていた。あまりに真剣に考え耽っていたために、僕は隣に座っている仲の良い友人の存在をふと忘れてしまう程だった。ただ、その友人は芸術や文学に造詣が深かったために、僕が友人の存在を薄すらと霧がかった場所へと追いやってしまっていても、許し見守ってくれていたのだろうと思う。それかもしかしたら、その雪の降る風景を眺めながら、僕と同じように何かの閃きの尻尾を掴みかけていたのかもしれない。とりあえず、なんだかそんなこと(閃きに尻尾がついていそうなくらいのことがね)が有り得そう夜だったということだけは確かなこととして記憶している。
そして、僕は六杯目のビールを注文しながら、一つの企画について友人に話をしだしたんだ。
僕「あのさ、こんな時に話することじゃないのかもしれないけど、善と悪というものがどういう意味なのか分かるかな?」
友人「そんなことを、こんな夜に一人で考えていたの?」
僕「まあ、ほんの五分くらいの時間なんだけどね。急に気になってきたんだよ。だってさ、善と悪について書かれてある本や、テーマとして扱っている作品はごまんとあるのだけど、そういうものを手にとってみても、僕にとっての善と悪というものが未だに形作られていないということを、まざまざと見せつけられていると感じるだけなんだよね。」
友人「それは、考えること自体がナンセンスだっていうことなんじゃないの?」
僕「じゃあ何故、人は考えてしまうんだろう?宗教の概念を飛び越えたところでも、それは歴史上ずっと繰り返されていることなんだよ?」
友人「自分の中に善と悪を持てないから、誰かの決めた善と悪を物差しとして生きていくんじゃない?そして、集団で生きていく動物として、それを誰かが作らないといけないという脅迫観念のようなものもずっとあるんじゃないかな?」
僕「そうだとするならば、宗教や社会や政治や集団やっていうありきたりの場所で決められることだけが、善と悪だってことになるよね?」
友人「でも、君だってさ、個人が私にとっての善と悪ということを心の中に持っていても、あまり意味がないことだというのは分かるよね?」
僕「そうだね。心の中にある善と悪の無意味さについては…考える余地もないくらいに。」
友人「だから、そういうことなんじゃない?」
僕「でも、こういう考え方をするとどうかな?仏教という宗教では自らが悟ることを良しとしている部分があるじゃない?勿論、それもあるルールやシステムの中での話だとは思うけどさ。ただ、自らが悟るっていう行為は、自らが個人的に善と悪について考えるということと似ているんじゃないのかな?」
友人「うーん。そうだね。でも、仏教徒も集団で修行をする中で考えていくということについては、他の宗教と変わりはないんじゃないかな?」
僕「そこには、与えられた答えの中で考えていくのか。それとも、与えられない答えの中で考えていくのかっていう違いがあるのかもしれない。」
友人「そうだね。似て非なる部分があるのは当然のことかもね。でも、何で急にそんな話をしだしたわけだい?君は芸術家なわけだし、哲学者でも歴史学者でもないのに。」
僕「僕が写真家だからかな。」
友人「そっか。やっぱり、僕からするち写真家って奴は何を考えているか分からない職業だよ。目の前にあるものをただ機械を通して写し続けていればいいのかと思いきや、そういう事だけで成立するものじゃないようにも見える。」
僕「僕は、僕の捉え方を他人に理解してもらうためには、とても使いやすいものだと思っているし、写真は言葉で解決出来ない問題についても足を踏み込むことが出来ると考えているのかもしれない。ただその前提に、とても矛盾してしまうんだけど、言語上での解決も必要だと思っている…のかな。」
友人「君のそういう矛盾しているところが僕も好きだけど、矛盾を一人で解決しようと思う傲慢さについては、少し難しいなと思っているよ。」
僕「だから今、君に相談してる。」
友人「僕は写真家じゃないから、君の相談には乗れても解決案を示すこととか、一緒に解決していくことは出来ないんだよ。」
僕「そうだね。とても、そのことに関しては悔しい思いを何度もしている気がするな。でも、だったら他人と…僕と僕ではない写真家とで考えていくことが出来れば、何かしらの解決とか結論のようなものは出てくると思う?」
友人「それは、やってみなければ分からないよ。」
僕「そうだね。今、僕が考えていることを少しでも理解してくれるのを前提に、写真家としての活動や思想にも距離がある人となら、やってみる価値はあるのかもしれない。」
友人「うん。僕もそう思うよ。一人で何時間、何ヶ月、何年間と、探していても見つからないものでも、違う目線で探すとすぐに見つかるってことがあるからね。」
僕「そうだね。誰がいいかな…。善と悪について、大きな問題意識ではなくて、写真や写真的現象の中から繊細に考えていける人で、間違えを恐れない人。今のこの企画の場合だと、間違いを恐れないということが一番大事なことだと思うんだよね。」
友人「言葉を変えさせてもらうと、間違うことを前提にと言ったほうがいいんじゃない?」
僕「間違うことを前提に、自らの善と悪や、写真の善と悪について足を踏み入れることが出来る人…」
友人「…」
僕「…三野君かな。」
友人「あの、演劇の?」
僕「そうそう。現代においては善き写真家ではないということが、彼を新しさに導いている気がするし、写真以外のものにも造詣が深いというのは、今回のこの話をする上でとても大事なような気がするんだよね。」
友人「そう思う人が、彼以外にいないのであれば、それはまさしく直感的にやるべきとしていいんじゃないかな。ただ、まだ僕は彼のことを知らないから、どういう形になるのかの想像もつかないけどね。」
僕「でも、その方が面白そうでしょう(笑)?」
友人「間違うことを前提にね(笑)」
僕「そうそう。それに、彼の名前は三野新だからね。新しいっていう名前だということが、先ず良いよね。だって善と悪、それこそが古いものなんだからね(笑)」
そして、七杯目のビールを注文した。その時点で、この企画は対談形式ではなく往復書簡形式とし、文章だけでなく画像や図形も送り合いながら話を進めていこうと頭の中で考えていた。僕は、まさに今閃きの尻尾を掴んだんだというような気持ちになり、一気に気分が好転していくのを感じていたし、これから始まる何かしらの写真的現象について期待していた。そして、早々に八杯目のビールを注文するタイミングを狙って、可愛い店員ではなく仕事の出来そうな店員の方向へと目を向けていた。勿論そこは、早く来いと念じながら。
二〇一三年十二月 秦雅則


